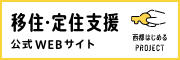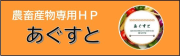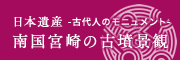市長コラム
市長が執筆し、広報さいとに掲載している市長コラムです。
令和6年度のコラム
vol.37(令和6年7月号掲載)市政報告会を開催して
先般、5月30日から6月7日にかけて、市内7地区(妻北、妻南、東米良、穂北、三納、都於郡、三財)で市政報告会を行いました。各地区いずれも30 ~ 40 人の参加をい ただきました。
私が再び市政を担当させていただいてから4年目となります。本当は毎年、各地区を回って報告会を行いたいと思っていましたが、これまでの3年間はコロナ禍のため、思うように開催することができませんでした。ようやく今年になって、区長の皆さまや公民館長の皆さまに参加をお願いし、また、市のホームページでも市民の皆さまにお呼びかけしました。その結果、幅広い年代の多くの皆さまにご参加いただきました。 報告会はパワーポイントを使用して"抜群に住みやすい西都づくり" と題し、主に9つの項目についてお話をさせていただきました。特に人口減少や少子高齢化に関する課題と対策、防災減災と危機管理対策、医療と教育問題、市財政の健全化、その他のトピックスなどをお話しいたしました。
その後、来場の皆さまから市政全般に対する貴重なご意見やご要望をいただきました。これらの内容については後ほど、ホームページや回覧板において皆さまにご報告させていただきます。
私はこれからも市民の皆さまや関係団体のご協力・ご支援を得て、これまで培わせてい ただいた豊富な経験と人脈をフルに活用し、使命感と責任感を持って、"愛と感謝の気持ち"で市政発展のため積極果敢にまい進してまいります。今後も皆さまのご指導をたまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。
vol.36(令和6年6月号掲載)市財政の健全化を目指して
私は前回の市長選挙において、公約の1つとして市財政の健全化を取り上げさせていた だきました。当時は令和2~3年にかけて新庁舎の建設が行われ、その後も公共施設の老朽化による更新や改修、統廃合などによる大きな財政負担や、高齢化社会の進展に伴う医療や福祉などの社会保障費の増大が予想されることを考えると、今のうちから健全な市財政を維持することが市民サービスの向上や市の活性化に繋がると思ったからです。
令和6年度の当初予算は一般会計が202億4千万円で、国民健康保険や介護保険などの特別会計は91 億2千万円となっており、毎年度、少しずつ増加しています。一方、令和5年度末の市債(借入金)残高は116 億7千万円、基金(貯金)残高は107億6 千万円でした。市債は令和3年度の125億3千万円をピークに少しずつ減少しており、基金は令和2年度の68 億5千万円から大きく増加しています。
この基金増加に最も貢献しているのが、ふるさと納税寄附金です。令和元年度が14億3千万円、令和3年度が23 億5千万円で、令和5年度には32 億8千万円と順調に伸ばしており、寄附金の約半分がふるさと振興基金として市の財源となります。
令和4年度決算に基づく市の財政状況を示す指数も良好で、市の借入金に対する将来負 担の割合も県内でトップクラスの健全な数値となっています。これからも市役所一丸と なって、効率的・効果的な各種事業に取り組むことで無駄な支出を減らし、また、ふるさと納税寄附金などの自主財源を増やし、国・県補助事業の積極的な活用を進めるなど、更なる財政の健全化を図ってまいります。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
vol.35(令和6年5月号掲載)西都児湯医療センター再建、本格的スタート!
西都児湯医療センターは、いまさら申し上げるまでもありませんが、住民が安心して暮らせる医療提供体制になくてはならない存在です。一次・二次救急医療、夜間急病センター、地域災害拠点病院の機能を有し、西都児湯二次救急医療の中核的医療施設としての役割をしっかりと果たせるものでなければなりません。医療センターにおいても、関係医療機関・団体などの協力を得ながらその充実に向け鋭意取り組んでいただいておりますが、市(市民)が求める目標に対し十分であるとはいえません。また、児湯郡の町村長からも、医療センターの充実に対する要望が届いております。
そのような状況の中、昨年度就任いただいた長田理事長が引き続き今期4年間の理事長に就任され、中長期的な医療センター再建に取り組んでいただけることになりました。 また、常勤医師確保につきましては、これまでの3人の常勤医師に加え、4月1日から44歳の総合内科(専門は循環器内科)の常勤医師に県立病院から着任していただきました。今後もさらに、常勤医師確保に向かって医療センターとともに努力してまいります。
このように、医療センターの前途に明るい兆しが見えてきており、この機を逃さず再建の柱である「常勤医師確保」、「経営改善」、「新病院建設」に邁進していかなければなりません。特に、市民の皆さま、また、西都児湯住民の皆さまの悲願であります新病院建設につきましては、市役所内に新たに新病院建設対策監(課長級)を配置し、基本計画策定に着手します。
私は、本年度を「西都児湯医療センター再建の本格スタートの年」と位置づけ、不退転の覚悟で取り組んでまいります。市民の皆さまのご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
vol.34(令和6年4月号掲載)ふるさと納税額が着実に躍進中!!
平成20年度から始まったふるさと納税制度ですが、令和4年度には全自治体での寄付金受入額の総額が約9,654億円に達しました。
本市においては、平成25年度に61件、183万8,000円であったものが年々増加傾向を示し、令和5年度(令和6年3月17日時点)には、17万6,509件、32億1,198万5,000円となりました。これは、本市を応援してくださっている多くの皆さまのおかげであります。また、いつも魅力的な返礼品を提供し、本市をPRしてくださる地元事業者のご協力と、市担当職員の日々の努力にも感謝申し上げます。本当にありがとうございます。市として引き続きふるさと納税の推進に努力してまいります。
このふるさと納税額の約50%がふるさと振興基金となり、「産業の振興に関する事業」、「青少年の健全育成および学校教育に関する事業」、「保健および福祉に関する事業」、「その他市長が必要と認める事業」に充当されます。これによって、市民サービスの向上や市政の発展に大いに役立つことになります。これからも市民の皆さまにおかれましては、市外・県外在住の知人にPRしていただきますようお願い申し上げます。私も市長名刺に返礼品写真やふるさと納税ポータルサイトの二次元コードを掲載して、積極的にアピールしております。
バックナンバー
■令和5年度
■令和4年度
■令和3年度
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | 秘書広報係 |
|---|---|
| 電話 | 0983-43-3110 |
| FAX | 0983-43-2067 |
| お問い合わせ | 秘書広報係へのお問い合わせ |